福岡県での安産祈願(戌の日参り)といえば、子安の杜宇美八幡宮が有名です。
毎年4月中旬ごろに行われる子安大祭や、戌の日には多くの参拝客で賑わう神社。
安産の神様として親しまれる宇美八幡宮では子安の石と呼ばれる縁起の良い石があるのはご存知かと思います。
今回はその子安の石には何を書いたらいいの?石に文字を書く場合はどうしたらいいの?という様な疑問をお持ちの方へ、宇美八幡宮の子安石の書き方について回答していきたいと思います。
- 宇美八幡宮の子安の石に何を書いていいか悩んでいる方
- 宇美八幡宮の子安の石には何を使って書くのが良いか悩んでいる方
- 宇美八幡宮の子安の石の返し方を知りたい方
- 宇美八幡宮の子安石の書き方
- 宇美八幡宮の子安石の返し方

以下の構成で進めたいと思いますので、気になる部分からお読み頂ければと思います。
宇美八幡宮の石の書き方は?

子安の石にはお子さんの出生日や名前などが書かれているのが一般的です。
書き方として記載順番が明確に定められている訳ではありません。
ではそんな子安石の風習が広まったかについて、余談にはなりすが、お伝えしたいと思います。
「子安の石」の由来は「鎮懐石」となることが、江戸時代に福岡藩の儒学者(貝原益軒)によって作られた地誌である「筑前国続風土記」に記されています。
身籠った神功皇后(じんぐうこうごう)が出兵する際に、戦が終わった後の安産を祈願し、お腹に巻いた2つの卵形の石が鎮懐石の由来とされており、無事に出産を終えた神功皇后がその鎮懐石を奉納したことが、子安の石の由来とされている様です。
ですので、無事に出産できたお祝いと健やかなる健康を祈って、安産を祈願した神社に石を納める風習が江戸時代から始まったのでは無いかと想像できます。
宇美八幡宮の子安の石は風習に基づいて以下の様な手順で取り扱われています。
- 安産祈願として他の方の石を持ち帰る
- 無事に出産するまで持ち帰った石に祈願する
- 出産を終えたら持ち帰った石と共に自分の石を奉納する
石に我が子の氏名等を記載する様になった時期については明確ではありませんが、奉納される石の数が多くなって、自分が納めた石が分かり易くなるように、名前が記載される様になったのかもしれませんね。
子安の石に書く内容は?
子安の石に何を書くかについては、宇美八幡宮の公式HPにおいても、お子様の名前等を記載しとある様に、明確に定まっていません。
我家も子供が2人いますが、どちらも記載した内容と順番は以下でした。
- 名前:フルネームで記載
- 性別:男の子と記載
- 生年月日:西暦で記載
- 体重:グラムで記載
- 願い:「優しく健やかに育ってくれますように」等の簡単なメッセージを記載
一般的にどんな内容が記載されているかも、実際の現場にて確認してみた結果は以下です。
(良く見かけた順番に記載しています)
- 生年月日、氏名、体重
- 生年月日、氏名、体重、メッセージ
- 生年月日、氏名、出生時間、性別、体重、メッセージ、イラスト
記載順番としては、生年月日、氏名、体重、メッセージという順番が多かったです。
生年月日については和暦と西暦の比率は半々な感じでした。
中にはメッセージと下の名前のみを記載している方もいらっしゃいましたよ。
子安の石の意味合いが安産の鎮めであること、これからの我が子の健やかなる成長の祈願であることを考えると、気持ちがこもっていれば、書く内容は自由で良いのではないでしょうか。
子安の石に文字を書くための準備
無事に出産を終えたら奉納する石に文字を書く準備をしていきましょう。
準備するものとしては以下の物を準備しましょう。
- 石
平たくて角が立ってない石が理想 - 洗浄する道具
ブラシやタワシ、油汚れが多い場合は中性洗剤 - 筆記用具
油性:ペイントマーカーやマッキー
水性:ブラックボードポスカやアクリル絵具(上手に書ける方や絵を楽しみたい方向け)
石
納める石は平たい石がゴツゴツした石よりも断然書きやすいです。
また、神功皇后の鎮懐石の由来を考えると卵形で、角が立たない人という意味も含めて、極力丸みをおびた石を選びたくなりますよね。
丸みをおびて平らな石は、山側よりも海に近い、中流~下流の川に多く見られます。

安定期に入ったら旦那さんと一緒に川辺を散歩しながら石を探し歩くのもいいですね
洗浄
川の石には砂やコケ、ぬめり等が残っているので、それらが残った状態で石に文字を書いても、上手く書けない・書いても剝がれやすいという状態になるため、ブラシやタワシを使ってこすり洗いをしてください。
こすり洗いをしても少しぬめりが気になるなと思ったら、中性洗剤を使ってぬめりを洗い流しましょう。
洗い終わったら、石の内部にも水分が含まれるので、日当たりが良く風通しの良い場所で十分に乾燥させてくださいね。
筆記用具
子安の石は屋外に奉納し、雨風にさらされることとなるので、耐水性のある筆記用部を選ぶ必要があります。
水性ですが、乾くと耐水性があるブラックボードポスカは一般のポスカより耐水性も高く、油性マジックに比べると臭いが少ないので、油性マジックの臭いが苦手な人には向いているかもしれません。
アクリル絵具も乾くと耐水性を発揮するので、筆を使って書きたいという方にはお勧めです。
宇美八幡宮の石の返し方もご紹介

無事に出産を終えて、石にも書くべきことを書いたら、これまで預かってきた石はどうすれば良いの?という疑問が沸いてくる方もいらっしゃるかと思います。
子安の石はお産の鎮め物であり、神様が祀られている神社にお返しする必要がありますので、間違っても近所の川に適当に置いたりしないでくださいね。
では、子安の石を神社にお返しする時期や場所、お返しするにあたって特別にやるべきことがあるのか等をご説明いたします。
子安の石はいつ返す?
子安の石は出産後いつまでに返す必要があるという様な期限は設けられていません。
当然ながら出産直後はお母さんは体力も落ちており、赤ちゃんもまだ外に連れ出さない方が良いと思いますし、慣れない育児で大変だと思うので、少し心が落ち着いてからお返ししにいくという感覚でいる方が、心にゆとりができて、穏やかな心でお返し出来るので良いと思います。
祝い事なので節目に行きたいという方は以下の神事を参考にしてください。
- 生後3日目:産湯
- 生後7日目:お七夜
- 生後31日目(男の子)・33日目(女の子):初宮参り
- 生後100日過ぎ:お食い初め
※地域により異なる場合があることご了承ください
どうしても早く行きたい方でも入院期間があるので、お七夜になると思います。
一般的には初宮参りの際に返納することを考えられる方が多いと思いますが、目安である出産1ヶ月後くらいのくらいはまだ母子共にデリケートな時期でもありますし、初宮参りも現代ではずらしても良いと言われているので、状況を見てから考えても良いと思います。
ちなみに我家は私の仕事の状況と奥さんの体調もあって、お食い初めに合わせてお宮参りをしてその際に返納しましたよ。
子安の石はどうやって返す?
返し方としては、初宮参りの祈願にてお祓いを受けたのちに子安の石にお返しするのが一般的と言われています。
宇美八幡宮は子安の杜とも呼ばれ、本殿以外にもお参りするスポットがありますので、ご祈祷を終えたら、以下の場所での参拝を行ってから子安の石を返すのも良いと思います。
- 子安の木:本殿左
- 産湯の水:本殿左奥の衣掛の森(大くすの木)の奥
- 聖母宮:本殿右奥の
- 湯方の社:本殿左奥
- 聖母子像:湯方の社(子安の石が奉納されたエリア)
子安の石はどこに返す?
子安の石はお借りした石と同様に本殿左奥の「湯方社(ゆかたのしゃ)」を囲む様に奉納されている、子安の石の上にお返しする様にしましょう。
子安石を納める本殿の裏は本殿を囲む様につながっていますので、本殿右側の駐車場や、本殿の裏からでもすぐにたどり着けますよ。
石を納める場所は多くの方の子安石が積まれていますので、その場所に崩れないように積み重ねましょう。
まとめ
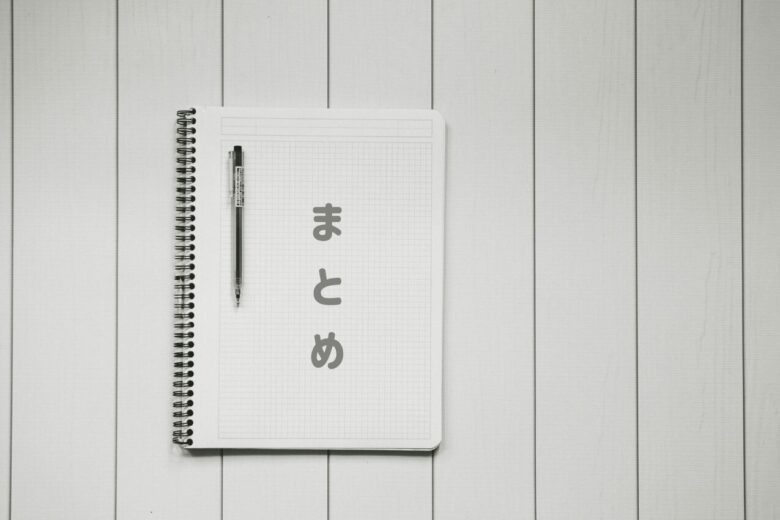
以上、宇美八幡宮の子安石の書き方と返し方をご紹介させて頂きました。
まとめは以下になります。
- 石の書き方に決まりはない
- 一般的には生年月日、氏名、性別、体重、メッセージが書かれている
- 石は洗浄して耐水性のあるペンで記載するのが良い
- 一般的に初宮参りでお借りした石と一緒に奉納する
- 一般的に安産御礼の祈祷を受けて子安の石を奉納する
- 子安の石は湯方の社にある子安の石の上に奉納する
書き方に決まりは無いので、我が子の無事を祈り気持ちを込めて書きましょう。
あなたが書いた石が次の妊婦さんに持って帰ってもらって、安産の流れが続くと嬉しいですね。
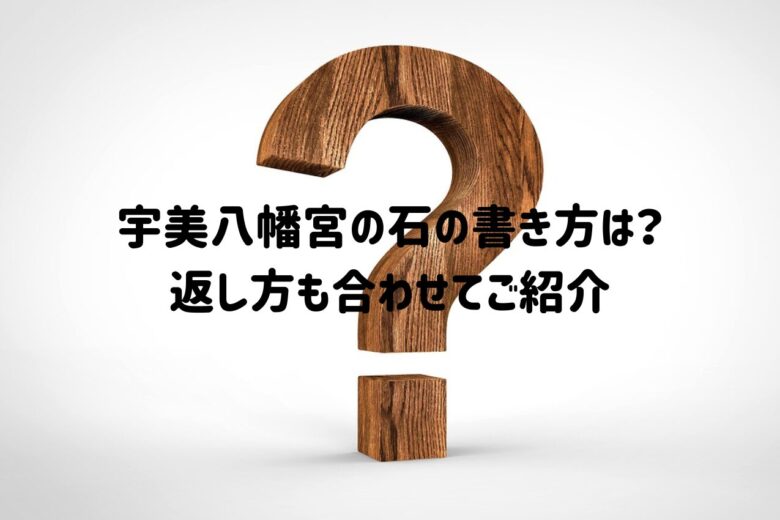
コメント